| DiscographyHitoshi's Works | |||
| Top / Profile / Blog / BUNNY CLUB / Discography / Shop / My Guitar / BBS / Movie(Youtube) |
|||
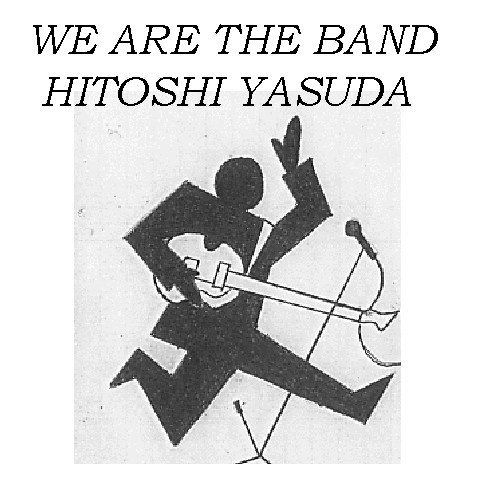 WE ARE THE BAND WE ARE THE BANDPRODUCED BY HITOSHI YASUDA 1990年作品 全曲作詞・作曲:安田 仁 レコーディング機材:4ch MTR「PORTA ONE」 (参加) 07:プリティー・ボイシーズ(Chorus) 12:小原聖基(Lead Guitar) |
|||
| (収録曲) 01.別れ告げたい 02.WE ARE THE BAND 03.COME BACK IN MY HEART 04.WORKER 05君のことなど忘れたよ 06.冷たい風が吹く街 07.あの娘の失恋 08.MY HEART 09.勇気だして 10.窓を開けてごらん 11.過ぎてしまえば 12.BEFORE DAY 13.僕らは明日を夢見てる |
|||
| (アルバム・レコメン) | |||
| 親愛なるバンド野郎に捧ぐ | |||
『WE ARE THE BAND』、このアルバムは安田氏の”アーリー3部作”の2部で、90年発表のアルバムだ。1stから一年後に発表されたが、まだまだヴォーカル、オケ共にピュアでチープな印象を受けざるを得ない。1stでは、彼の音楽的に影響が希薄な、ニューウェイブっぽい、80sの音がしていたが(まぁ、これは個人的な感想なので)、2ndはどうなんだろう・・・?『WE ARE THE BAND』、訳すと「俺達はバンドだ」もしくは「俺達のバンド」とも受け取れる。おぉ・・・!紛れもなく2ndは”バンドサウンド”だ。1stはわかりやすく言うとソフトで”優しい”感じのアルバム・イメージだが、本作はハードで”漢”(「おとこ」と読んで下さい)な感じのロック・アルバムだ。 彼はこの作品以降も自称”ロック・アルバム”と呼ぶ、ハードエッジな(と言ってもポップという範疇の中でだが)音のアルバムを何枚か出しているが、そんなアルバム群のルーツがこの2ndだろう。また新作『HARD WAY』のプロト・タイプ的な感じもして(これも個人的な感想)、12年のタイム・パラドックスを垣間見た気がする。こうやって彼の音楽性をクエストするのもおもしろいですよ、皆さん(笑)。 彼は度々、”前作での反省を生かした”アルバムや”前作とコンセプトの違う”アルバムを発表しているが、1stと2ndはまさに、それだ。80’s臭い所から脱却した60〜70’sのバンドのイメージをこのアルバムで見せつけている気がする。でもイメージこそ60〜70’sであっても、バブルガム・ポップやルーツ・オブ・ハードロックを鳴り響かせているのではない。もうそれは既に”仁サウンド”なのだ。フィルターを通して出している音はそんな感じだ。歌詞の方もエピキュリアン(享楽主義者)な彼らしい所が出てきたような感じがするし・・・。トータルコンセプトは”バンド”・・・しかも60〜70’sのバンドイメージ・・・音的には70〜80’sのオールド・ウェイヴ、ドラム音はドラムマシーンの「ポコッと感」が80’sテクノ・・・そんなのがミックスされた感じだ。初期仁サウンドはまさにそうだ。 よく安田氏の知人は彼の音楽性の引き合いに「ビートルズ/ポール・マッカートニー」を引用しているが、僕の中では全く別物だし、引き合いにもならんと思うんだけどなぁ・・・(??)。僕の解釈じゃ「ハンキー・ドリー」の頃のデビッド・ボウイやエルビス・コステロの臭いがする、そう・・・エンターテイメントな感じの所がね。このアルバムはロック・アルバムと言っても激しいモノではないし、安田 仁という人物がアジテートする、エンターテイメントだ。僕、個人的な話で申し訳ないですけど、ビートルズは好きだけど、”ビートルズ好き”は嫌いなんですよ、安田 仁も含めて(笑)。なーんか音楽の話になるとビートルズありきで話して、ビートルズと比較して・・・比較された方はイヤだと思うよ、僕ぁ。ビートルズに無くて、その人に有る所・・・安田氏の音楽とビー(以下略、笑)の音楽を比較するなら、僕はそういう所を見つけたいです。クローンじゃないんだから、申し子かもしらんけど・・・(笑)。 ・・・と言うワケで安田氏の2ndはビー(以下略)の様じゃなくて、もっとエンターテイメントされた楽しいR&Rアルバムです。ビー(以下略)やポール・マッ(以下略)の音、っていう閾値を突破した仕上がりになっています。ポップの粋から脱輪していないが、ドリーミー(笑)な感じでもなく・・・う〜ん、言うなれば諸教混淆、シンクレティズムを経た、仁流魂のアルバム(言いすぎか?)と言った所か。黎明期に96℃あたりでグツグツとたぎっている安田 仁のロックへの熱い情熱・・・そんなところを感じてもらえたらいいのになぁ〜と思っています。この2ndは、もう絶対的に『WE ARE THE BAND』なのだ。何者でもない、安田氏の音がここで鳴っている。(野間 久史) |
|||
| 音楽的衝動 「WE ARE THE BAND」from『WE ARE THE BAND』 |
|||
アルバム中の歌詞カードを見てもらえると分るのだが、本アルバムの中には、安田仁が自ら初期の代表曲と認めながら、同時に封印することを宣言した奇妙な曲がある。タイトル曲「WE ARE THE BAND」がそれである。この曲は、当時彼が結成していたバンドでライヴを行うことを念頭に作られたもので、ありし日の思い出と共に封印したというのがその経緯であるらしい。当時から安田仁に近い人たちにとっては納得のいくことなのだろうが、私のように後になってからこの曲に触れたものにとっては、「なんでこんないい曲が封印されんの、勿体無い・・」などとつい思ってしまうのである。なぜなら、この曲は単に名曲であるというに留まらず、安田仁というミュージシャンのあり方を端的に示しているという点において、彼を象徴する重要な曲であり、初期の代表曲という彼の評価から「初期」という限定を取り除いても一向に差し支えないほどの曲である、といえるからである。 音楽の素晴らしさとは何か、という問いかけをしたとき、端的に答えるのは中々難しい。答えは一つだけのようにも思えるし、人によって千差万別であるとも考えられるからである。結局答えは、自分なりに答えるしかないのだろう。私にとっては音楽の魅力を一言でいうと、「衝動」になる。すなわちそれは、理論でもなく、経験でもなく、理由もなく、客観性も多数決による裏づけも無いが、心の琴線に触れる曲、歌詞、歌い手などに出会ったときに内側から自分を突き上げてくる強い力である。 これは、確かに具体的でも理論的でもなく、自分の演奏や歌に対する評価とさえいえないものかもしれない。しかし、自分が歌や演奏が、誰かの音楽に対する衝動を掻き立てたのだとすれば、表演者にとってこれに勝る喜びはないのではないだろうか。音楽の「楽」しさを伝え、共に分かち合うことに成功した証であるといえるからである。 それは逆に、私自身が安田仁の音楽に接する度に抱く思いである。私は安田仁の音楽に対し、技術面や理論面で解説する能力を有していないし、そのような意欲を持っているわけでも無い。ただ、彼の音楽に触れ、衝動のままに聴き、口ずさみ、「いいね」という単純な感想を口にするのみである。自分にとってはむりやり言葉で糊塗するよりもその方がずっと自然に聴けて心地いい。ただ衝動のままに聴けるからこそ、私にとって安田仁の曲は、長く付き合える大事な存在であり続けているのだろうと思う。 今回取り上げた「WE ARE THE BAND」は、まさにこの「衝動」を歌詞の中で巧みに表現している曲である。「場所など気にしないで どこでだって歌うさ」、「喜び溢れるなら 声張り上げて 歌い続けよう」などといった、簡単な言葉で綴られたフレーズの中に、音楽の魅力や音楽への衝動がどれほど含まれていることか。それは、言い換えれば安田仁がポップスというジャンルで目指そうとしているもの、ライヴで目指そうとしているものの一つの在り方であり、この曲は曲としての完成度のみならず、テーマにおいても、安田仁の象徴となりうる名曲といってよい。 願わくは、リメイクとまではいかなくとも、ライヴでの再演などを検討して貰いたいものだ。すごくライヴ映えする曲だと思うのだが。 |
|||
| <ALBUM> MYSTERIOUS HANDS / WE ARE THE BAND / KICK THE SUN ! / SHOOT / BRILLIANT GAME / ACTION ! / LIVE MAN / ROND ROUND ROUND / SKETCH MUSIC / HARD WAY / Dr.ポップの逆襲!!/ GET BACK TO THE FINE DAY / SELECTIONS & PRESENTS / FLASH BACK / ボクの宇宙 / Friendship |